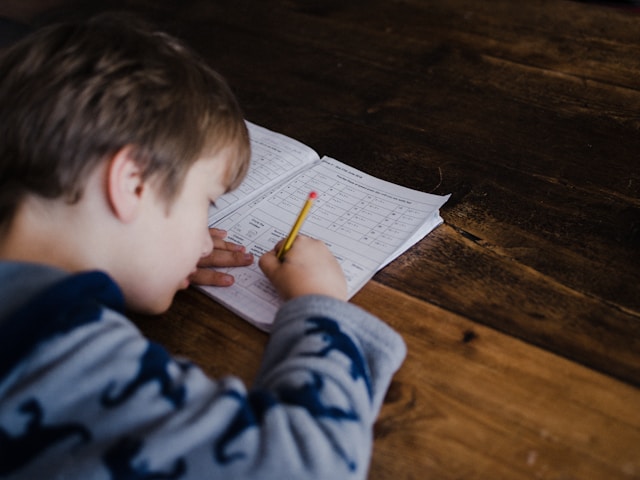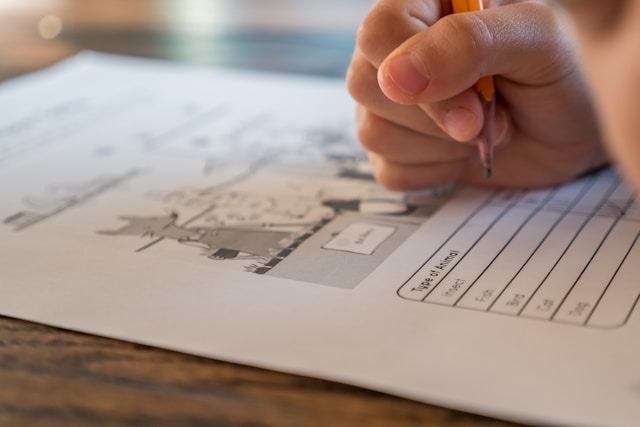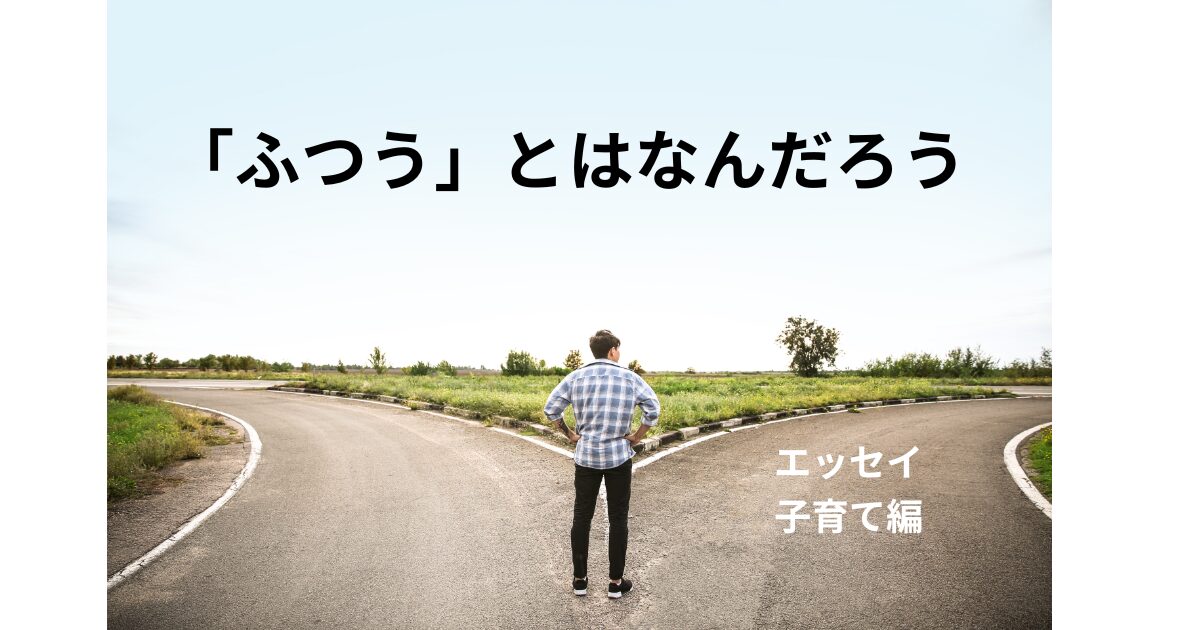お雛様はもう、うちにいません

母からの「雛人形を買いなさい」問題
子どもの節句の一つである「ひな祭り」。初めて孫を持った(私の)母にとって節句は大きな出来事だった。
私が娘を出産したとき、母が「これでお雛様を買いなさい!」とお金を渡してくれた。実はこのような節句モノ(雛人形)を持ちたくないと思っていた。
私の“ひな祭り”の思い出は、けっこう曖昧だった
実家には七段飾りの立派な雛人形があったが、毎年きちんと飾られていたわけではない。母は「いつも飾りたいと思うけれど、大変だから」と言っていた。たしかに押入れの奥に入っているし、七段飾りなので飾るにも片付けるにも手間がかかるのだ。
私は雛人形がなくてもひな祭りを迎えられるタイプだったし、飾る手伝いをするのがいやなので出さない選択をありがたいと思っていた。
やっぱり私は、大きな雛人形に馴染めなかった
雛人形に思いれなく過ごしてきたので「子どもにも雛人形をあげたい」という気持ちにはなれなかった。どちらかというと「どうせ出すのが面倒になるから、そんなものは必要ない」と思っていた(雛人形の値段も高額だし)。
一応、雛人形にもなにかしら意味があって買うのだろうと調べてみたら、大まかに3つあるらしい。
- 女の子の厄を払う
- 幸せな結婚を願う
- 健康で元気に成長することを祈る
お雛様もこんな期待を背負わされてるのかと思うと大変だ。
私はゴタゴタが起きたとき、お雛様を憎んだりはしなかったし、お雛様をちゃんと飾らなかったからだと思ったことははない。
しかし母はどうしても孫の雛人形が気になるみたいで、「どんな雛人形を買ったんだ?」とお金をもらってからは雛人形を買うまで会話のトップトピックスになっていた。
結局ほどいい値段のガラスケースに入った雛人形を購入した。それでもなかなかの大きさでウンザリしていた(コンパクトなものは値段が高くなるのだ)。
購入してからも、しばらく(2−3年)は「ちゃんとお雛様飾ったの?」と聞かる始末。私はこの会話に多少なりとも疲れていた。こんなに聞かれたりするなら自分のお金で買えばよかったとも思ったけれど、きっとそれは母からすれば嫌だろう。母は“孫に雛人形を買ってあげた”という事実が大事なのだろうから(たぶん)。
子どもも無関心──それならもういいかな、と思えた日
その後ゴタゴタがありムダに大きなお雛様と一緒に引っ越した。引っ越す準備をしているときに改めて「お雛様はいらない」と感じた。引っ越すたびにこの大きなお雛様を連れていくのは気が重すぎる。
そこで「お雛様を廃止」とまではいかないけど、もっと小ぶりなお雛様にチェンジしたくなった。
決意後の3月に「この雛人形を飾るのは今年で最後にしよう」と気合を入れて段ボールから重くて取り出しにくい雛人形を飾りました。
「どうだ」と子どもに見せたけど、子どもはまったくといっていいほど食いつかなかった。
その様子に拍子抜けの私。でも最後だからと思い「お雛様飾ったよ、きれいだね」と子どもに伝えたけど「わーほんとだ」と言ったきり、すぐテレビにかじりついていた。
無関心な子どもを見てお雛様を買いなおす必要性を感じなくなりました。
「ひな祭り」をしない選択も、家族らしい形かもしれない
その後「ひな祭り」はいつもの日常として過ごしている。なにも特別でもない日。雛人形も飾らず(雛人形はさよならした)、ちらし寿司も食べず、歌も歌うことなく終わる。
子どもから「雛人形は?」と聞かれないし、母からも「雛人形は?」と聞かれなくなった(さよならしたことを察したのだろう)。
節句を大切にするのも素敵でしょう。でも無理せず、自分たちに合った形で節句と付き合うのも一つのあり方だと思う。