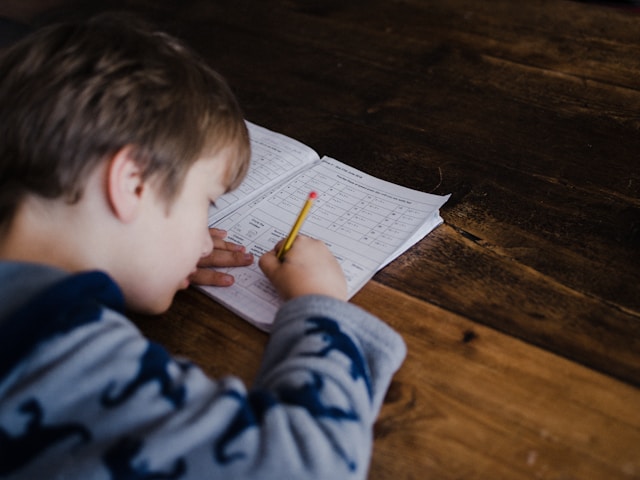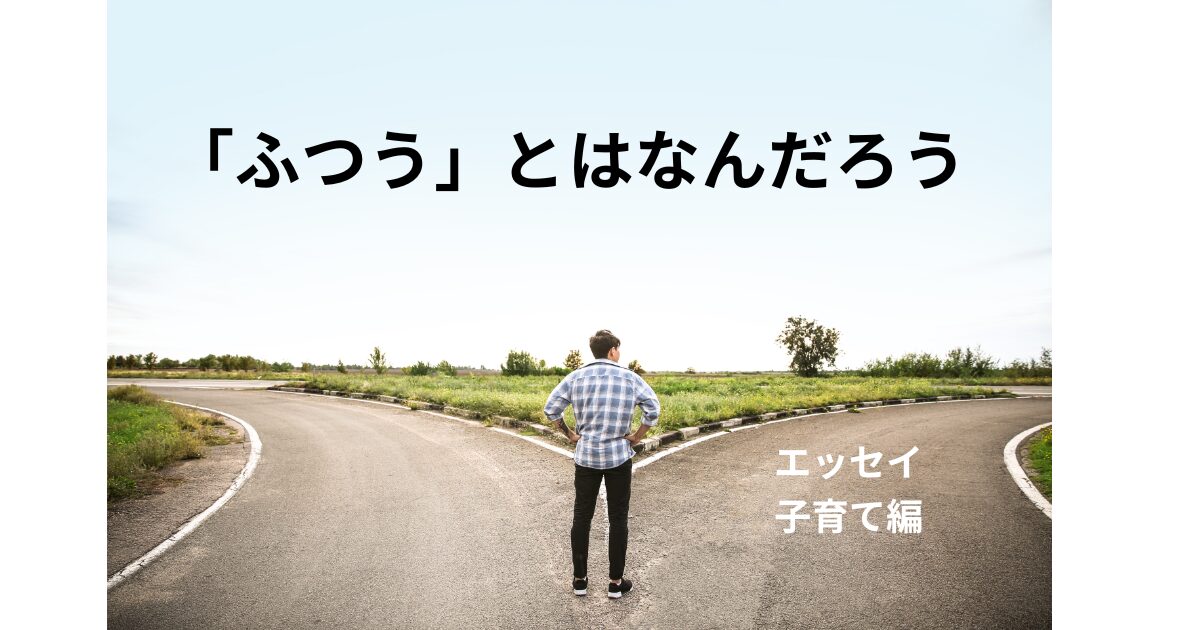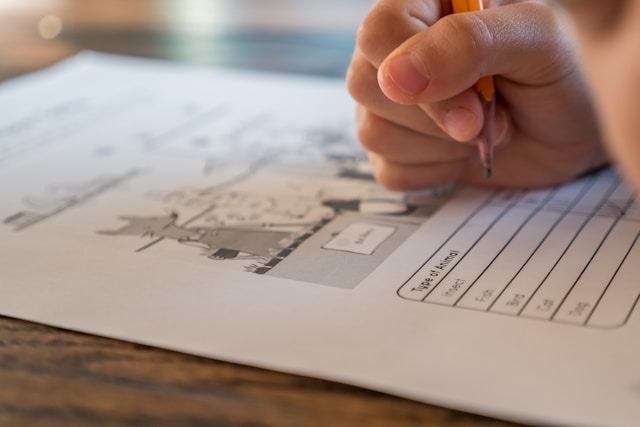季節の変わり目に出てくる“夏の疲れ”と、子どもの登校しぶり

暑すぎた夏がようやく終わった――はずなのに、どっと疲れが出てくるのはなぜだろう。
季節が変わるたび、心も身体も少しずつほころびながら整っていく。
子どもも、大人も、夏の余韻の中でもがいているのかもしれない。
夏の疲れ
本格的な秋が近づき、涼しくなってきた。そして、過ごしやすくなると同時に夏の疲れが顔を出し始めた。
この夏もカラダが溶けるように暑かった。なんど外に出ることを躊躇しただろうか。街の空気はまるでサウナ状態、なにをするにもすぐにグロッキーになってしまった。いつまでこの暑さは続くのだろうと、うんざりした気持ちでやり過ごしていたら急に涼しくなった。
いままで半袖・半ズボンという元気な小学生のような格好で過ごしてきたけれど、最近は寒すぎてそのような格好はできない。こうして、夏の暑さをすぐに忘れるのだ。
断捨離癖
私は夏になると冬服を捨てたくなる。暑すぎる夏を過ごしていると、このまま冬は来ないのではないかと思ってしまうのだ(もちろん、夏がどんなに暑くても冬はやってくる)。
夏の暑い日に洋服を断捨離すると「今後ダウンを着る機会はないだろう」と本気で思う。でも、冬になるとしっかりダウンを着るし、ダウンなしでは冬は越せないことを知っている。
洋服の断捨離は、シーズンの終わりに着なかったものを捨てるのが一番だ。夏の暑い時期には冬服を、冬の寒い時期には夏服を断捨離してはいけない。
喉元過ぎれば熱さを忘れる
何回も暑さ・寒さを経験しているのに、その季節の温度を忘れてしまう。忘れてしまうものといえば「季節の変わり目の疲れ」もだ。
涼しくなってくると、疲れたなと思うことが増えてくる。
「そうか、夏の疲れが出てきたんだ」と思うけれど、よく考えたら、暑さの真っ最中も疲れていたし、梅雨の頃もぐったりしていた。もしかすると、年中疲れているのかもしれない。(どこで体力を削られているのやら。ふぅ。)
毎日のように「どうしたら疲れないカラダになるか」を考えてるし、巷で勧められていることもやっている。それでも疲れるものは疲れるのだ。大人のエネルギーはすぐに消耗してしまう。
子どもだって疲れが出てくる
大人はエネルギーがすぐ切れるものだから仕方がないと思っていた(割り切った)が、子どももエネルギーが切れるみたいだ。朝になると「学校行くのがメンドウ」と言う。そんなことを言われると心配になるから、熱を測ってみるけど平熱。食欲もいつも通り。
つまり気持ちの問題。でも、その気持はとてもわかる。
「ほんと行きたくないよね」と私も頷くが、休む理由が「なんとなく行きたくない」では休んでも解決することはない。たとえ今日、学校へ行かなかったとしても、明日からは行くことになるだろう。そして、一日休めば学校へ行きたくなるわけではない。
学校へ行くことは子どもにとって必要なことだ。
ズル休みに対する背徳感
子どもが「行きたくない」と言ったとき親としては、学校へ行かなくなったらどうしようと考えてしまうもの。強く「学校は行かないとダメ」と言えたら楽だろうけれど、「ムリして行かなくていいよ」と言うのがいいことを知っている(無理させると、どこかで糸が切れたようになってしまうかもしれない)。
別の考え方をすると、「ズル休み」をすることで生じる背徳感を知ることも大事だろう。
ズル休みをしても大して面白くないことを知ってほしい。そして、学校へ行ったほうが気持ちが清々しいものになることも。行って後悔したことはない。そもそも行かないといけない場所なのだ。
そのことを知るのもいいのかもしれないと頭の中でグルグルと考えている間に、学校へ行く時間になる。子どもは「学校へ行く」と言って渋々玄関を出て行った。
別に休んでいいのにと思いながらも、ホッとする自分もいる。
そんな子どもを見て、夏の疲れが気持ちに出ているのかもと思った。涼しくなってくると、暑さで張り詰めていた気持ちがプツッと切れるような気がする。涼しさによって、気持ちが開放されて「疲れ」に気づきやすくなるのだろう。
ホッとしたのもつかの間。子どもが学校から帰ってくると「行かないほうがよかったのかも」とか言い出した。
もしかすると、これは夏の疲れだけではないのかもしれない。子どもの気持ちはやっぱり難しい。いや、子どもに限らず——自分以外の誰かの気持ちを理解するのは、いつだって簡単なことではない。
最後までお読みいただきありがとうございます。
季節の変わり目、なんだか疲れが抜けないな…と感じること、ありませんか?
子どもだけでなく、大人の私たちも、気持ちが揺れる時期かもしれませんね。